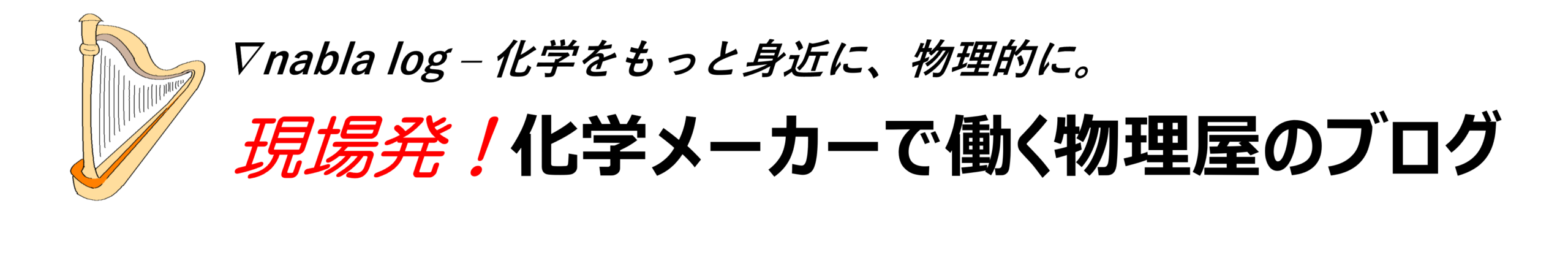「赤外分光法といえばFT-IR」と言われるくらい、FT-IR(フーリエ変換赤外分光法)は研究室から工場まで広く利用されています。
しかし、「ボタンを押すだけなので、よくわからない間にIRスペクトルが得られている」という方も多いのではないのでしょうか?
FT-IRには特徴的なプロセスとして、マイケルソン干渉計、試料室、フーリエ変換の3つがあります。このページでは、FT-IRのユーザーが知っておくべきこれらの測定原理をご紹介します。
- マイケルソン干渉計は分析を容易に行うために存在する
- 試料が受ける熱量を減らすように試料室を設置する
- フーリエ変換ではFFT(高速フーリエ変換)が利用されている
FT-IRの構成について
FT-IRは「フーリエ変換(Fourier Transform)と、赤外光(Infra-Red rays)を利用して物性を調べる方法」で、大きく3つの重要プロセス(マイケルソン干渉計、試料室、フーリエ変換)を経ることでスペクトルを得ています。

- マイケルソン干渉計でのインターフェログラム生成
- 測定試料によるIR吸収
- フーリエ変換によるスペクトル作成
以下、マイケルソン干渉計から順に化学者が押さえておくべきFT-IRの重要プロセスをご紹介します。
マイケルソン干渉計
FT-IRで重要な工程として「マイケルソン干渉」があります。


マイケルソン干渉は高校物理の「波動」分野で聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

FT-IRでマイケルソン干渉計を設置する理由は、赤外光を直接試料に当てるよりも分析を容易に行うためで、透過光を簡便に観測できる関数(後に説明する「インタフェログラム」)を作るためです。
なぜマイケルソン干渉計が必要なのか
マイケルソン干渉計を用いず、連続スペクトルを直接試料に当てて、吸収された光の波長を調べることは原理上可能です。
しかし、その場合は時間の関数$I(t)$として透過光を観測するため、フェムト秒オーダーで光の揺らぎを観測する必要があり、装置が高コスト、大がかりになります。
マイケルソン干渉計を挟むことで、時間$t$ではなく、光学距離差$h$の関数として光を観測することになり、「手をかけずにIRスペクトルを得たい」という化学者のニーズを高度過ぎない技術力で対応できるようになります。(日本分光学会 測定法シリーズ 「フーリエ変換赤外分光法」によると、$1\text{cm}^{-1}$のオーダーでスペクトルを知りたい場合は、最大光路差を$1\text{cm}$程度取ればよい)

波長$\nu$の光(強度$B(\nu)$)を距離差$h$のマイケルソン干渉計にあてたとすると、装置出口での光強度(振動分)は$B(\nu)\cos(2\pi\nu{h})$になります。全ての波長による寄与を足し合わせるとインターフェログラム$I(h)=\int\text{d}\nu{B}(\nu)\cos(2\pi{i}\nu{h})$になります。
計算はこちら

このインターフェログラムは$\cos$を多数足し合わせた形をしているので、$h=0$を中心に極大を持ちつつ、$h$の増大とともに急激に減衰する偶関数になります。

試料でのIR吸収
マイケルソン干渉計を通ったあと、赤外線は試料に照射されます。
マイケルソン干渉装置出口での光強度は装置出口での光強度(振動分)は$B(\nu)\cos(2\pi\nu{h})$になので、試料の透過率を$T(\nu)$とすると、試料照射後の強度は単純に$T(\nu)B(\nu)\cos(2\pi{i}\nu{h})$となります。

FT-IRでは、参照試料と測定対象に対して赤外線を透過させたときに得られるインターフォログラムのわずかな違いを元にIRスペクトルを作成します。


このわずかな違いを抜き出すために行うのが、後のフーリエ変換です。
透過光のスペクトル計算はこちら
試料透過後に観測されるインターフェログラムは、(複数の波長の合成波なので)$I(h)=\int\text{d}\nu{T}(\nu)B(\nu)\cos(2\pi{i}\nu{h})$となりますが、これはフーリエ変換後の関数$\tilde{T}$と$\tilde{B}$を利用すると$I(h)=\int\text{d}h^\prime\widetilde{T}(h^\prime)\widetilde{B}(h-h^\prime)$と表すことができます。


なぜマイケルソン干渉計の後に試料を置くの?逆でもよさそうだけど

マイケルソン干渉計の後に試料を置くメリットとして、試料が受ける熱量を減らせることが挙げられます。
計算上は試料⇒マイケルソン干渉計の順でも同じインターフェログラムが得られますが、マイケルソン干渉計の後に試料を置く(後置)場合、(マイケルソン干渉計での損失分だけ)試料が受ける熱量を少なくできます。(「日本分光学会測定法シリーズ フーリエ変換赤外分光法」には後置のメリットだけでなく、デメリットも記載あり)
フーリエ変換
もともと得たかったのは振動数ごとの吸収特性であり、インターフェログラム$I(h)$ではありません。そのため、試料出口で観測されたインターフェログラム$I(h)$をフーリエ変換することで、知りたかった試料の吸収スペクトル$I(\nu)$を得る必要があります。

これがFT-IRの「FT(フーリエ変換)」の部分だね

実際には、試料がない場合と、試料がある場合の2つの差分を調べることで吸収スペクトルを得ています。
フーリエ変換ではFFTと呼ばれる「高速フーリエ変換」が利用されています。(通常のフーリエ変換をDFT(離散フーリエ変換)と呼ぶことにします。)
FFTとDFTの主な特徴は次の通りです。FFTではDFTよりもアルゴリズムが複雑であるなどのデメリットがあるものの、DFTよりも圧倒的に早いという最大のメリットからFT-IRのみならずフーリエ変換といえばFFTが利用されるケースがほとんどです。
- FFTはDFTよりも圧倒的に早くフーリエ変換できる(例、DFT:40分、FFT:3秒)
- FFTではデータ点数が$2^n$に縛られる
- FFTではDFTよりもプログラミングが複雑(例、DFT:30行、FFT:70行)

まとめ
このページでは、FT-IRのユーザーが知っておくべきポイントとして、マイケルソン干渉計、試料室、フーリエ変換の3つのポイントをご紹介しました。
「赤外分光法といえばFT-IR」と言われるくらい、FT-IR(フーリエ変換赤外分光法)は研究室から工場まで様々な場所で利用されています。
直接試料に当てる場合は、フェムト秒オーダーでの測定器が必要ですが、FT-IRではマイケルソン干渉計を挟むことで、低コストと高性能を両立していることを知っていただければと思います。