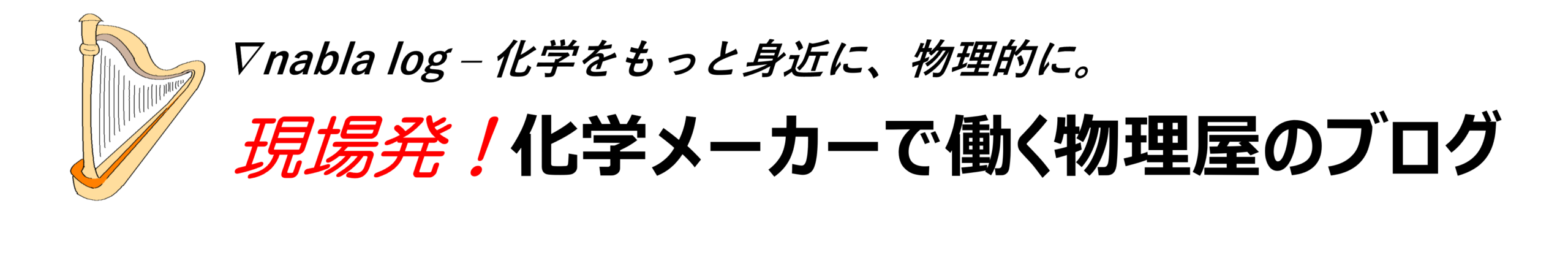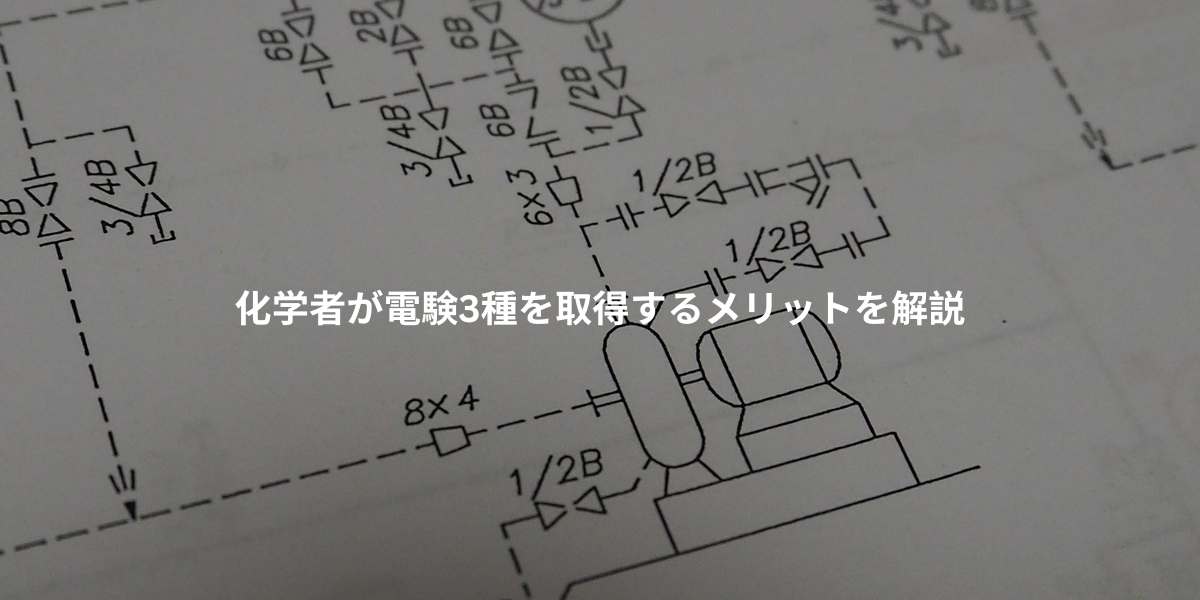第三種電気主任技術者試験(電験3種)は化学工場などに設置されている電気設備の保守・監督を行うための資格です。
電験3種は化学者にとって資格を取得する意義が無いように感じられますが、実は、化学工場の機械の動作原理や特徴を効率よく勉強できる良資格です。また、化学以外の分野の資格になるので、資格取得によって専門領域を広げることもできます。
このページでは、電験3種の試験内容(理論、機械、電力、法令)が化学者にとってどのように役立つかを中心にご紹介していきます。
電験3種の出題範囲
まずは、電験3種で問われる内容をご紹介します。電験3種では「理論」、「機械」、「電力」、「法令」の4本柱で試験が構成されます。

化学者目線では、この「理論、機械、電力、法令」の順で知識を活かしやすいと感じます
| 出題される問題例 | 化学工場で役立つポイント | |
| 理論 | 3相交流回路の計算問題(電流値、電力値など) | 「3相交流」という言葉に親近感が湧く |
| 機械 | 誘導機に関する計算問題(すべり、動力値) | ポンプや撹拌機で活躍する誘導機モーターに詳しくなれる |
| 電力 | 電力降下に関する問題(送配電) | 進相コンデンサーの意味・意義がわかる |
| 法令 | 接地抵抗に関する問題 | 機械や建物の接地抵抗の意味・意義がわかる |
次から、これらの分野が化学者にとってどのように役立つかをご紹介していきます。
理論
電験3種において、最難関の科目は「理論」と言われる場合が多いです。
3相交流回路に面食らう方は多いのではないでしょうか?

実際、電験3種の理論では次のような問題が出題されます。


なんだこれ、、電流がどう流れるかさえ分からん。。

3相交流の回路は単相回路に書き換えられるので、実は簡単な問題です。
化学専攻の方の多くは直流回路の知識で止まっている方が多いかもしれません。しかし、化学工場だけでなく、産業機器のほとんどは3相交流回路で動いています。
つまり、化学工場の機械を知るためには3相交流の知識は必須です。電験3種の理論を勉強することで、この必須の3相交流に関する知識を得ることができます。

(イオンの駐車場にあった1.5kWモーター)
さらに、身の回りの鉄塔をよく見ると、電線の本数は必ず3の倍数(6本や12本)になっています。なぜなら、発電所などからも3相交流を使って送電するので、3の倍数になるためです。


化学者の身の回りにも3相交流はありふれています。電験3種の「理論」を勉強することで3相交流を身近に感じられることがメリットです。
機械
電験3種で化学者が「機械」分野で最も勉強になるのは誘導機の分野です。電験3種の「機械」を勉強することで、誘導機に関する基本的な用語や計算を効率よく学ぶことができます。


このホームページでは誘導機を何度もご紹介していますが、「全ての化学工場には誘導機がある」といって過言ではありません。
誘導機の「基本のき」は「回転速度」「すべり」「極数」です。これらを知っていれば、化学メーカー勤務の化学者にとっては一定以上の理解度があると言えるでしょう。ポンプには次のような銘板がくっついていますが、電験の機械を勉強することで「定格出力」、「極数」といった用語に全く苦手意識が無くなります。

例えば、電験3種の機械では、次のような問題が出題されます。
定格出力7.5kW、定格電圧220V、定格周波数60Hz、8極の三相誘導電動機がある。この電動機を定格運転すると82N・mのトルクが発生する。この時の電動機の回転速度[min-1]を求めよ。
H20 電験3種(理論)より(一部改編)

定格運転?分からん。なんならkWの単位にはアレルギーがある

定格、極数、滑りといった誘導機の基本さえ知っていれば難しくはありません
一方で、「機械」分野には誘導機以外に直流機、同期機、変圧器といった機器の計算も勉強する必要があります。残念ながら、化学者にとってこれらの機器の知識は活かしにくいのが事実だと思います。

例えば、化学者が同期機に関わることは稀でしょう(動力などにはあるが、保守はメーカーに一任も多い)
しかし、これらの機器ももちろん社会ではありふれているので、身の回りにある電気の仕組みに強くなれるのがメリットかと思います。
電力
残念ながら、電験3種の「電力」で問われる内容は、化学メーカーで働いている多くの方にとって縁遠いです。

しかし、電験2種の2次試験では「電力」の分野は「機械」よりも出題数が増えるので、電験の主役であったりします。
電力の分野では「送電線で電圧値がどの程度低下するか」などの計算が問われます。(化学者にとってあまりなじみがないかと思いますが、電圧値は変電所から工場に至るまでの間で変化します。)
例えば、電験3種の電力では次のような問題が出題されます。

工場では電圧を変化させないために、進相コンデンサーと呼ばれる機器が設置されています。

進相コンデンサーは家庭用だとプラモデルくらいの大きさですが、工場用だとミニバンくらいの大きさになります
電験の電力分野を学ぶことで、工場や家庭の電気が発電所・変電所からどのようにして届いているかを計算を元に知ることができるのがメリットです。
法令
高圧ガスの資格試験でも法令が問われるのと同じように、電験の試験でも(電気事業法に関する)法令が問われます。
法令に関する問題のうち、化学者にとって関連が深いのは接地抵抗に関する計算問題です。例えば、過去には次のような問題が出ています。
電動機に完全地絡事故が発生した場合、(中略)対地電位が30Vを超えないようにするために、(中略)D種設置工事の最高限度値[Ω]の値として、最も近いのは次のうちどれか。(後略)
H16年 電験3種 法規より
電動機に異常が発生した時に、サンプリングしている運転員や立ち合いをしている開発員が感電しないためには、接地が必要不可欠です。この接地抵抗が一定以下になるように金属棒や板が地面に埋められています。

意識してプラント現場を歩くと、接地抵抗に関する銘板があったりします。
その他にも、家庭の$100\text{V}$電圧は実は$101\pm6\text{V}$の幅で維持されていることや、人が高圧電線の電磁誘導作用を感知されてはならないことが決められているなど、生活の安全性が電気事業法によって守られていることを知れることもメリットです。
まとめ
このページでは、電験3種の試験内容(理論、機械、電力、法令)が化学者にとってどのように役立つかを中心にご紹介しました。
電験3種は化学者にとって資格を取得する意義が無いように感じられますが、実は、化学工場の機械の動作原理や特徴を効率よく勉強できる良資格です。また、資格取得によって化学以外へも専門領域を広げることもできます。
一朝一夕では取得が難しい資格ではありますが、電気に少しでも興味がある方はぜひチャレンジしてみましょう。