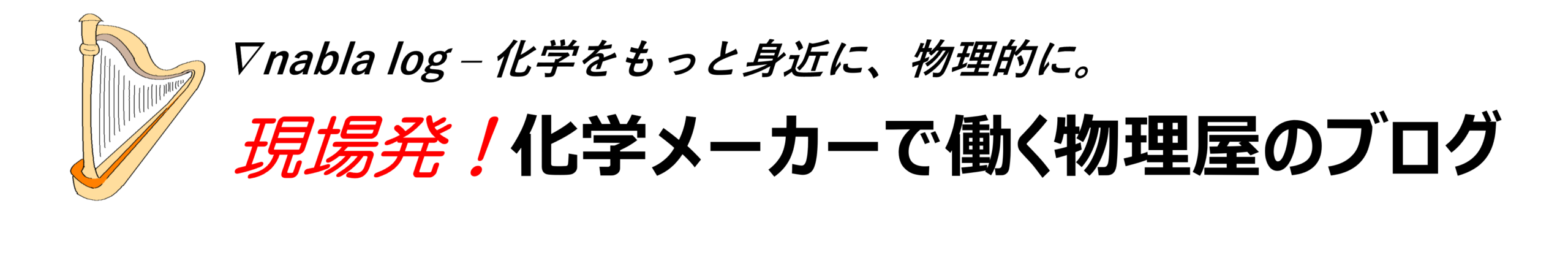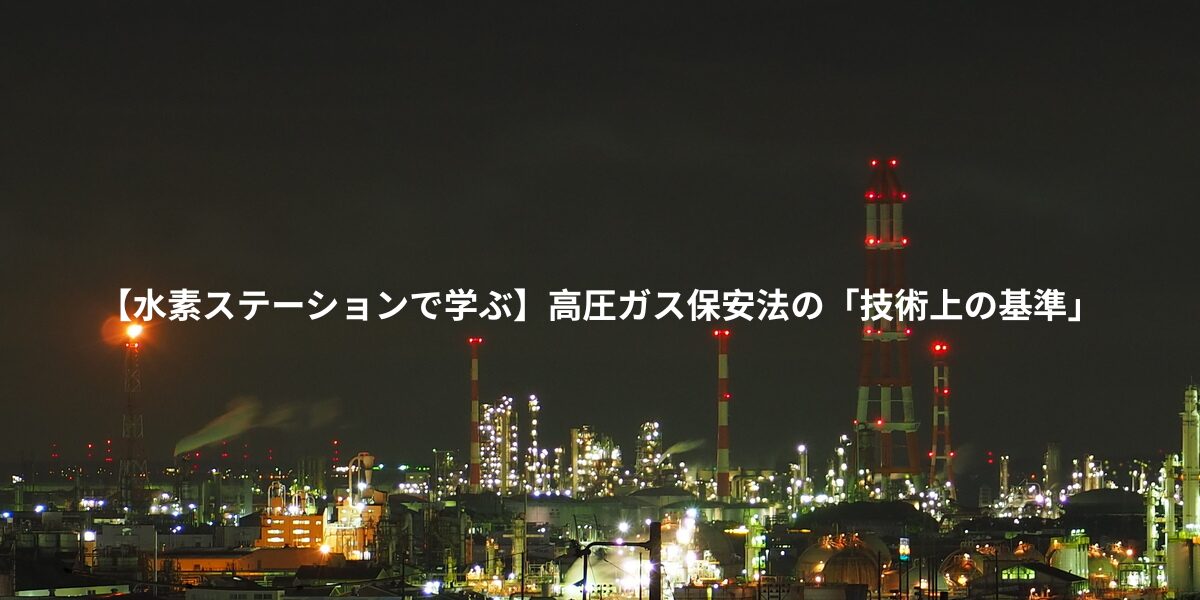皆さんは水素カー(燃料電池自動車)に乗ったことがありますか?
水素カーは燃料である水素を水素ステーションで補充する必要がありますが、この水素ステーションでは非常な高圧状態(800気圧程度)にした水素を取り扱います。
一般的な窒素ボンベなどの圧力が150気圧程度なので、水素ステーションがいかに高圧の水素ガスを取り扱っているかが分かるかと思います。このページでは、高圧ガス状態にある水素の安全性をどのように担保しているかについて解説していきます。
このページでは令和7年8月時点での高圧ガス保安法を参照して水素ステーションの「技術上の基準」を紹介しています。
水素ステーションの規制は変更ペースが早いため、技術上の基準を調べる際は最新の法令をご確認ください。
水素ステーションは高圧ガス保安法の規制を受ける
水素カーは2022年8月時点で7,418台しか普及していませんが、2030年には80万台の規模にするロードマップが描かれています。(経済産業省「モビリティのカーボンニュートラル実現に向けた水素燃料電池車の普及について」令和4年9月より)

なお、中間時点の2025年には20万台規模にする計画ですが、2024年時点で8,479台しか普及してません。(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suisohou_01.html)

経済産業省がんばって!
水素カーの普及計画の実現には疑問が残りますが、この水素カーに燃料である水素を供給するのが「水素ステーション」です。この水素ステーションでは80MPaG(800気圧)程度という、とんでもない高圧状態の水素ガスを取り扱うため、高圧ガス保安法の適用を受けます。

1MPaG以上のガスは高圧ガス保安法を受けます。自転車のタイヤで0.5MPaG程度の空気圧です。

80MPa程度の水素を取り扱う水素ステーションのすごさがわかるね
水素ステーションが高圧ガス保安法によってどのような規制を受けているかを知るため、埼玉県所沢にある水素ステーションに行って観察してきました。

水素ステーションにはいくつか種類がある
水素ステーションは高圧ガス保安法の規制を受けますが、実は、水素ステーションにはいくつか種類(郊外型or都市型、セルフ式or対人式など)があり、それぞれ規制の内容が異なります。
幸いにも、訪問した所沢にある水素ステーションは許可年月日を掲示していたので、高圧ガス保安協会が公開している報告書を元に水素ステーションの種類を知ることができ、所沢の水素ステーションは「高圧ガス保安法 一般則第7条の3第2項」の規制を受けているものとわかりました。



許可日が一致するものを探した結果、「一般則第7条の3第2項」の適用を受ける水素ステーションなことが分かるね

「一般則第7条の3第2項」とは、「大容量」「都市型」「対人式」の水素ステーションのことです

写真から「技術上の基準」の具体例を見てみましょう
高圧ガス保安法の適用を受ける施設は、「技術上の基準」というものをクリアしないと許可を得ることができません。さらに、許可を得た後も一年に一度、行政(埼玉県や検査機関)が行う保安検査で「技術上の基準」が維持されているかの確認を受け続ける必要があります。
水素ステーションがクリアしなければならない「技術上の基準」は膨大です。敷地外からでも分かるものでも多くの規制がありますので、実際にどのようなものがあるか紹介していきます。

水素ステーションの技術上の基準(号の数)は80項目程度あり、敷地外から分かるものは12項目でした。


それでは順番に「技術上の基準」を見ていきましょう。
1号(警戒標)
事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
一般則 第6条第1項第1号(抜粋)
水素ステーションは高圧ガスを作っている場所(高圧ガス製造施設)なので、そのことが一目でわかるよう、警戒標を掲げる必要があります。

歩道に向かって立っている赤い看板が警戒標だね
2号(ディスペンサーの位置)
ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し八メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
一般則 第7条の3 第2項(抜粋)
ディスペンサーとは、水素カーに水素を入れるための操作盤のことです。水素ステーションでは、ホースなどにピンホールが開いて水素が噴出した時でも敷地外に影響を及ぼさないよう、ディスペンサーと公道の距離を一定以上離す必要があります。


水素ステーションの常用圧力が82MPaの場合は8m、93MPaの場合は8.5mの距離が必要です。
4号(防火壁)
圧縮水素スタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設けること。
一般則 第7条の3 第4項(抜粋)
まわりに民家などが多い都市部に水素ステーションを作る場合、防火壁として2m以上の壁を作る必要があります。

一方で郊外に水素ステーションを作る場合(一般則第7条の3第1項の水素ステーションとなる場合)、この規制は不要となります。
9号(配管の措置)
配管は、次に掲げる措置を講ずること。
一般則 第7条の3 第9項(抜粋)
ロ トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。
水素の特徴として、「圧倒的に軽い」という特徴があるため、漏れ出た際に上方が閉じていると水素ガスがたまってしまいます。そのため、トレンチ(溝)の中に配管を通す場合、通気性のよい蓋を使う必要があります。

18号(火災検知警報)
ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
一般則 第7条の3 第18項(抜粋)
普通、ものが燃えていると「炎」として人は感知できますが、水素の場合、燃えていても可視光が出ないので、目には見えません。
そのため、ディスペンサーの周りには火災を検知できる機械を設置する必要があります。

所沢の水素ステーションでは、ディスペンサーの上部に黒い火災検知器がついていました。

21号(自動停止装置、温度上昇防止措置)
製造設備の運転を自動的に停止する装置と自動的に温度の上昇を防止するための装置は、火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
一般則 第7条の3 第21項(抜粋、一部改編)
ディスペンサーには、水素の供給停止と温度上昇防止(例えば散水)を操作できるボタンを設置する必要があります。

23号(車両の衝突防止措置)
ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
一般則 第7条の3 第23項(抜粋)
水素ステーションの場合、ガソリンスタンドと異なり、ディスペンサー周りを柵で防御する必要があります。

この柵の強度は例示基準によって「20km/hrの速度でぶつかっても壊れない程度」とされています。
24号(ディスペンサーの屋根)
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
一般則 第7条の3 第24項(抜粋)
配管のトレンチでも話しましたが、水素は漏れると上方に漂っていきます。もし、ディスペンサーの屋根が逆コの字のような形だと、水素に逃げ場がなく、たまってしまいます。そのため、ディスペンサーの屋根にはすき間ができるような工夫などがされています。

25号(充填ホースの破損防止)
ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講ずること。
一般則 第7条の3 第25項(抜粋)
R7年時点で水素ステーションで水素カーがホースをつないだまま発信してしまい、危険な状態となった事故は発生していないですが、LPガスのローリーなどでは誤発進による充てんホースの引っ張り事故などが発生しているため(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/2023_kouatsujiko_ichiran.pdf)、誤発進しても大量に水素が漏れ出ないよう、緊急離脱カップリングがホースの先端についています。

31号(消火設備)
圧縮水素スタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
一般則 第7条の3 第31項(抜粋)
水素ステーション内で火災が発生した時、水素設備に影響が出る前に消化する必要があります。そのため、水素ステーションには消火器を常備しておく必要があります。


水素の燃焼火災対策というよりは、外部(車など)による火災対策の位置づけと思われます。
33号(容器置場)
容器置場及び充塡容器等は次に掲げる基準に適合すること。
一般則 第7条の3 第33項(抜粋)
イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ 容器置場は、その外面から、敷地境界に対し八・五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
ハ 充塡容器等に係る容器置場には、直射日光を遮るための措置を講ずること。
ニ 可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ホ 可燃性ガスの容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
ヘ 容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
最後に、容器置場ですが、警戒標の設置や車両衝突防止、滞留防止など、ディスペンサー周辺と同じような規則が要求されています。


水素ステーションの「技術上の基準」ってこんなに多いのか。疲れたよ

冒頭でも紹介した通り、これまで紹介したものでも全体のうちのほんの一部です。
まとめ
このページでは、高圧ガス状態にある水素を取り扱う水素ステーションが高圧ガス保安法によって、どのように規制されていいるかについて紹介しました。
水素ステーションは経済産業省が普及に力を入れているため、高圧ガス保安法の中でも改定されるペースが早いです。
これからどんどん水素ステーションが身の回りで増えていくと思われますので、動向を見守っていきましょう。