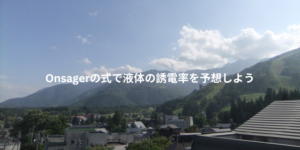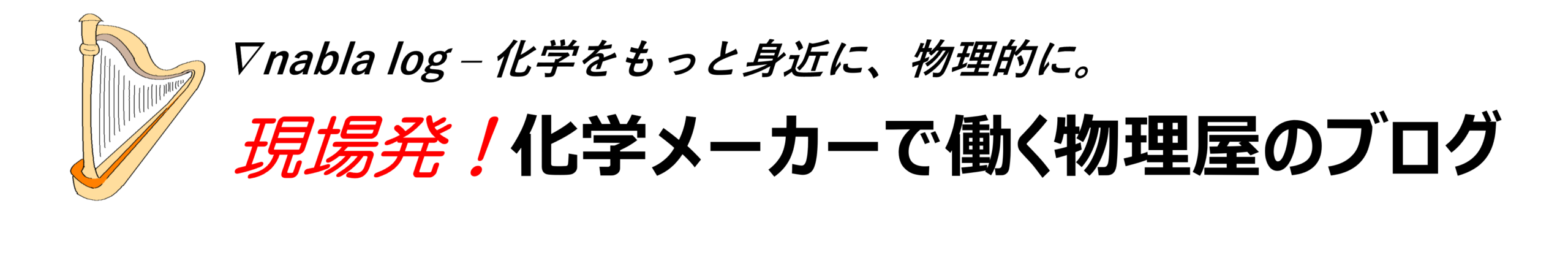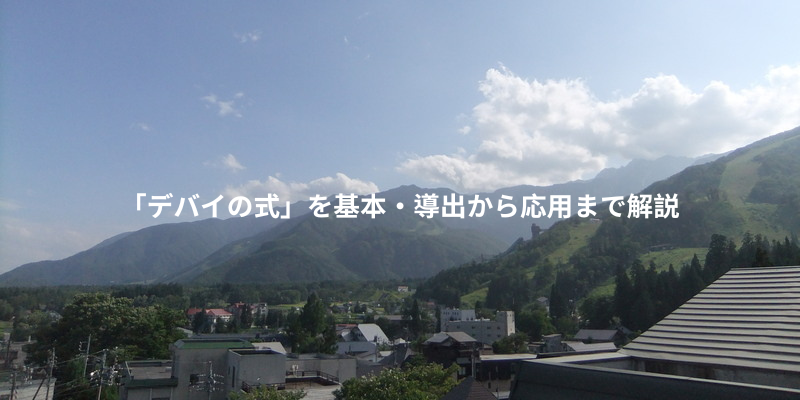「デバイの式」は分子の極性を表す比誘電率$\epsilon_r$と分子の電気的性質である双極子モーメント$\mu$、分極率$\alpha$を定量的に結びつける基本的関係式です。
デバイの式は$\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}=\frac{\rho{N_A}}{3M\epsilon_0}\Bigl(\alpha+\frac{\mu^2}{3k_BT}\Bigl)$で与えられますが、$-1$や$2$などが混在し、どこからこれらの値が出てきたか私ははじめ全く分かりませんでした。
このページでは、双極子モーメント$\mu$と分極率$\alpha$の復習から始めて、誘電体理論の基本式である「デバイの式」を導く導出方法を解説し、ショウノウへの利用例まで紹介します。
- 双極子モーメントと分極率の定義を紹介
- 「デバイの式」の導出方法を詳しく解説します
- ショウノウに「デバイの式」を適用し、双極子モーメントなどを計算します。
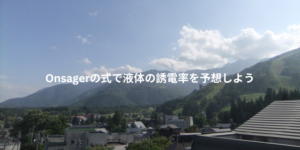
【復習】双極子モーメントと分極率について
双極子モーメント
「双極子モーメント$\mu$」は化学者にとって結構なじみのある言葉ではないでしょうか?
異なる原子(例えば酸素Oと水素H)が化学結合するとき、電気陰性度の高い原子に電子が引き寄せられるために、電子の偏りが生まれます。この電子の偏りを表す量が(永久)双極子モーメント$\mu$です。

(永久)双極子モーメント$\mu$は外から電場を分子に書けなくても分子が永久に持っている電気的性質なんだね。
分極率
「分極率$\alpha$」は化学者にとってなじみが少ない方も多いのではないでしょうか?
分極率$\alpha$は双極子モーメント$\mu$の兄弟のようなものです。電場$E$を分子にかけると、永久双極子モーメント$\mu$とは別の双極子モーメント$\mu^\prime$(誘起双極子モーメント)が誘起されます。誘起双極子モーメント$\mu^\prime$の発生率を表すのが分極率$\alpha$と呼ばれるものです。$\mu^\prime=\alpha\cdot{E}$

多くの電子を持つ分子(つまり大きな分子)はその分動ける電子も多いので分極率$\alpha$は大きくなりやすいです。
デバイの式
双極子モーメント$\mu$や分極率$\alpha$はミクロな世界の物理量なので、直接測定することは困難です。そのため、実験的に求められる比誘電率$\epsilon_r$を経由して求める必要があります。

比誘電率$\varepsilon$はコンデンサー容量の測定から調べられます。
この双極子モーメント$\mu$と分極率$\alpha$(ミクロな量)と比誘電率$\epsilon_r$(マクロな量)をつなぐ式が「デバイの式」$\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}=\frac{\rho{N_A}}{3M\epsilon_0}\Bigl(\alpha+\frac{\mu^2}{3k_BT}\Bigl)$です。
デバイの式を導くための仮定は次の2つです。
- 局所的には1つの分子の周りの分子配向はランダムとする(つまり分子間相互作用を無視する)
- 誘電率測定時の電場は十分小さいとする
証明はこちら
Debyeの式は誘電体内部に半径$a$の空隙を考えることで導出できます。


補足1

補足2

この式を利用することで、様々な温度$T$で測定した比誘電率$\epsilon_r$を用いて、$\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}$を$\frac{1}{T}$に対してプロットすることで未知量である双極子モーメント$\mu$や分極率$\alpha$を求めることができます。
デバイの式は分子間の相互作用を無視して得られているので、液体や高圧ガスのような系に対しては成り立ちません。
実際の測定結果(ショウノウ)
実際に、ショウノウ(分子量$M=152.23\text{g}/\text{mol}$)の実験結果を使って、双極子モーメント$\mu$と分極率$\alpha$を求めてみましょう。
デバイの式を変形した$\frac{M\epsilon_0}{\rho{N_A}}\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}=\frac{\mu^2}{3k_B}\frac{1}{T}+\alpha$を利用します。
測定結果はこちら
| $θ[/℃]$ | $\rho[\text{g}/\text{cm}^3]$ | $\epsilon_r[-]$ |
| 0 | 0.99 | 12.5 |
| 20 | 0.99 | 11.4 |
| 40 | 0.99 | 10.8 |
| 60 | 0.99 | 10.0 |
| 80 | 0.99 | 9.50 |
| 100 | 0.99 | 8.90 |
| 120 | 0.97 | 8.10 |
| 140 | 0.96 | 7.60 |
| 160 | 0.95 | 7.11 |
| 200 | 0.91 | 6.21 |
$\rho$と$\epsilon_r$の測定結果を用いて、$\frac{M\epsilon_0}{\rho{N_A}}\frac{\epsilon_r-1}{\epsilon_r+2}$を$\frac{1}{T}$に対してプロットすると、傾き$4.65*10^{-37}$、切片$3.68*10^{-39}$の直線が得られます。

この傾きと切片を利用することで、双極子モーメントは$\mu=\sqrt{3k_B*4.65*10^{-37}}$$=4.38*10^{-30}(\text{C}\cdot\text{m})=1.33(\text{D})$で、分極率は$\alpha=3.68*10^{-39}(\text{C}\cdot\text{m}^2/\text{V})$$=3.31*10^{-23}(\text{cm}^3)$であることが導かれます。

単位に注意しましょう。
まとめ
このページでは、双極子モーメント$\mu$と分極率$\alpha$の復習から始めて、誘電体理論の基本式である「デバイの式」を導くための仮定と詳細な導出方法を解説し、ショウノウへの利用例まで紹介しました。
「デバイの式」は$2$や$3$の係数や、$+$と$-$の符号が混在しますので、導出方法がわからなくなったらまたこのページで確認してください。
一方で、液体溶媒には「デバイの式」は使用できず、分子間力を考慮した「オンサガーの式」を使う必要があります。「オンサガーの式」は別のページで紹介していますので、そちらもよろしければご確認ください。