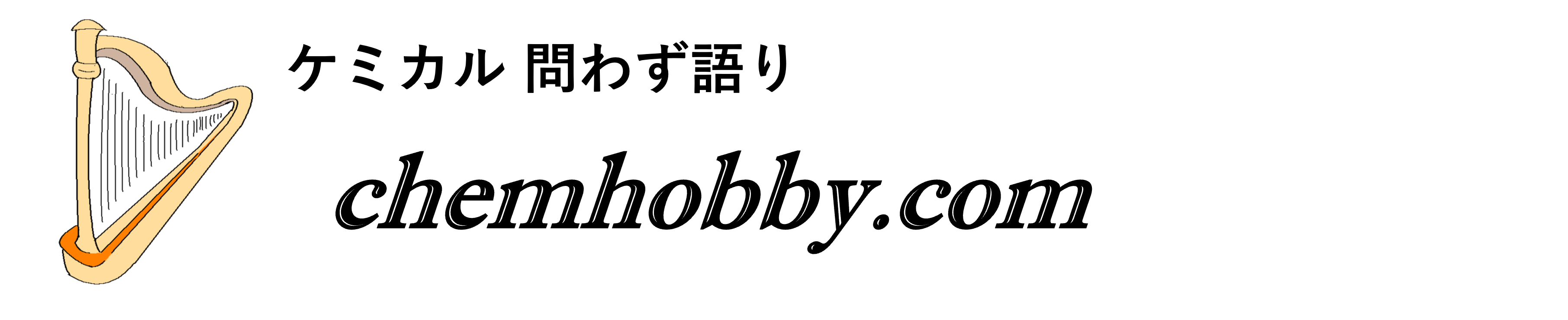熱力学– category –
-
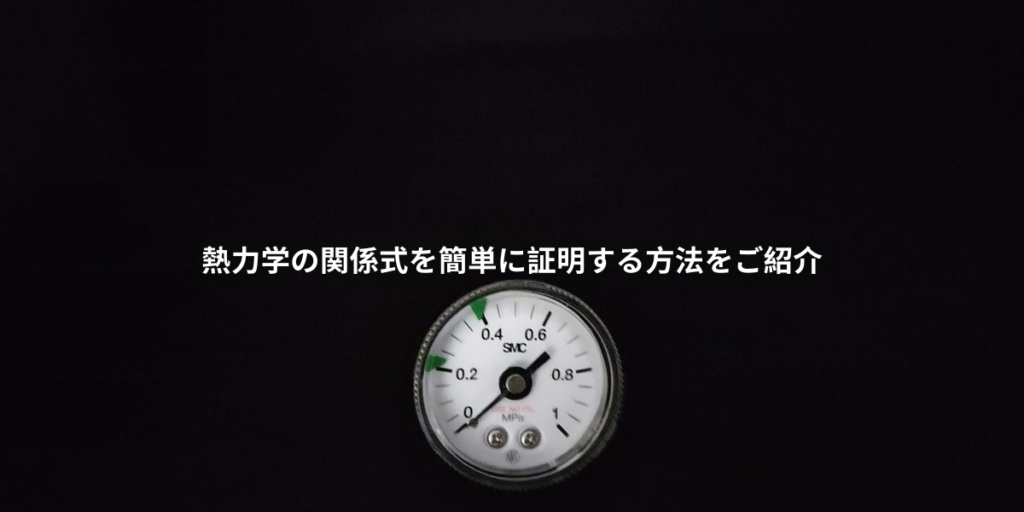
【コツがある】熱力学の関係式を簡単に証明する方法をご紹介
大学の定期テストや大学院入試では熱力学の関係式を示す問題がよく出題されます。 熱力学の証明問題はMaxwellの式や自然な変数、偏微分の公式などをいつ、どのように使うか分かりにくいので、難しいと感じていませんか? しかし、実はほとんどの熱力学の関... -
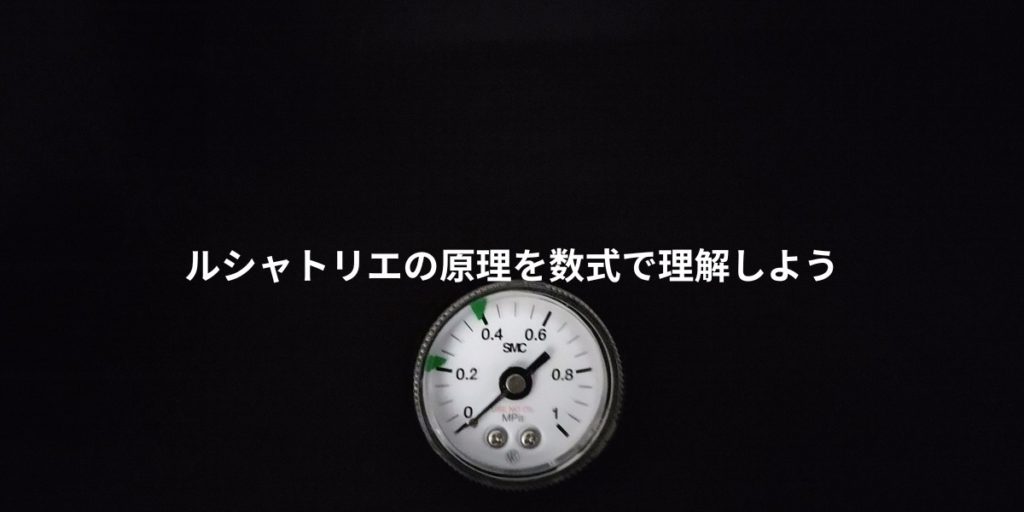
【化学界の金字塔】ルシャトリエの原理を数式で理解しよう
ルシャトリエの原理は「自然は変化を嫌う」というおしゃれで定性的にも理解しやすい原理です。(なお、提唱者の化学者「アンリ・ル・シャトリエ」はおしゃれ人が多い?フランスの方です) 高校化学では、この原理を定性的に利用して化学平衡を取り扱います... -
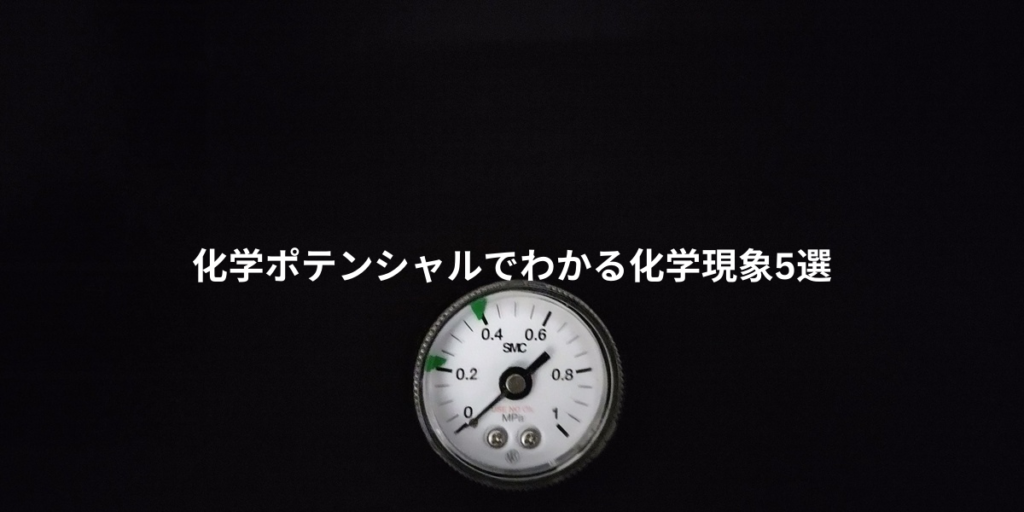
【広い守備範囲】化学ポテンシャルでわかる化学現象5選
化学ポテンシャルは化学において黒子のような存在ではないでしょうか? 例えば実験やプラント設計の際に物質の化学ポテンシャルを考える方は稀だと思います。しかし、化学ポテンシャルは化学平衡定数などの原理を示してくれるので、「普段は意識されないけ... -
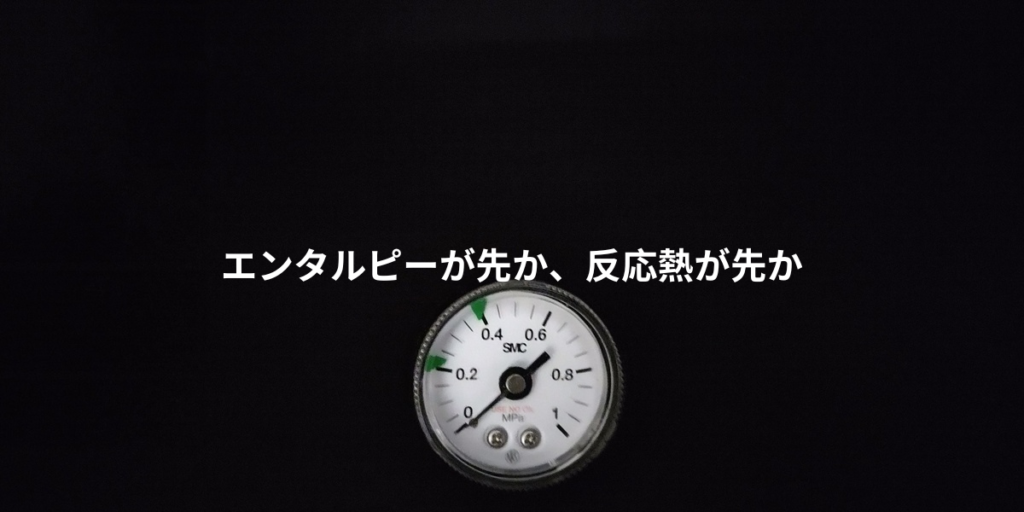
【化学者の疑問】エンタルピーが先か、反応熱が先か【捉え方の違い】
エンタルピーはH=U+pVで定義され、物理学的には他の自由エネルギーと対等なものですが、化学者にとっては反応熱に関係するため、特によく目にするエネルギーです。 皆さんは「エンタルピー差は反応熱を表す」のか、「反応熱がエンタルピー差になる」のか、... -
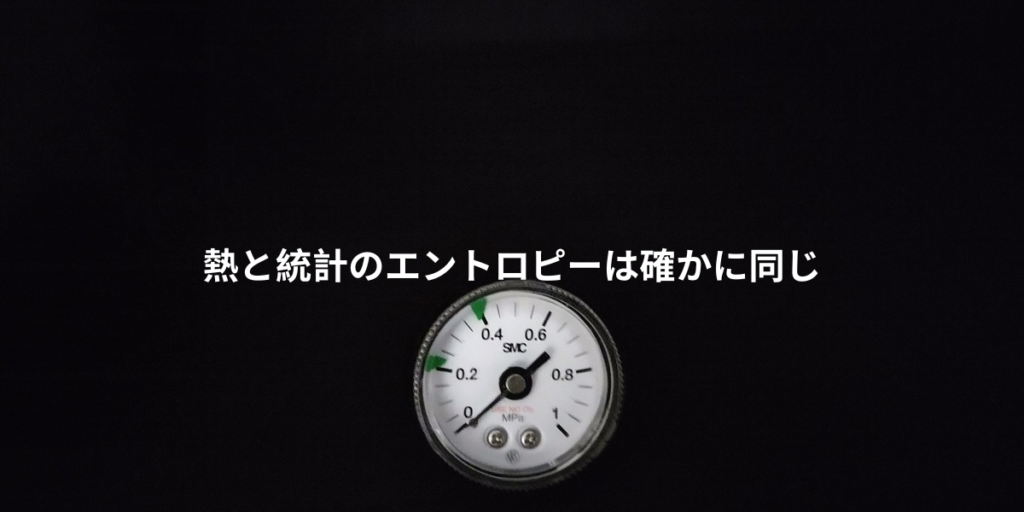
【乱雑さと言うけれど】熱と統計のエントロピーは確かに同じです
化学熱力学の教科書で「エントロピーはS=kB log Wで与えられ、乱雑さを表します」と熱力学の冒頭で書きつつも、そのあとはdS=dQ/Tでの計算しか出てこず、乱雑さはどこにいった?と思ったことはありませんか? エントロピーは熱力学からはdQ/Tで与えられ、... -
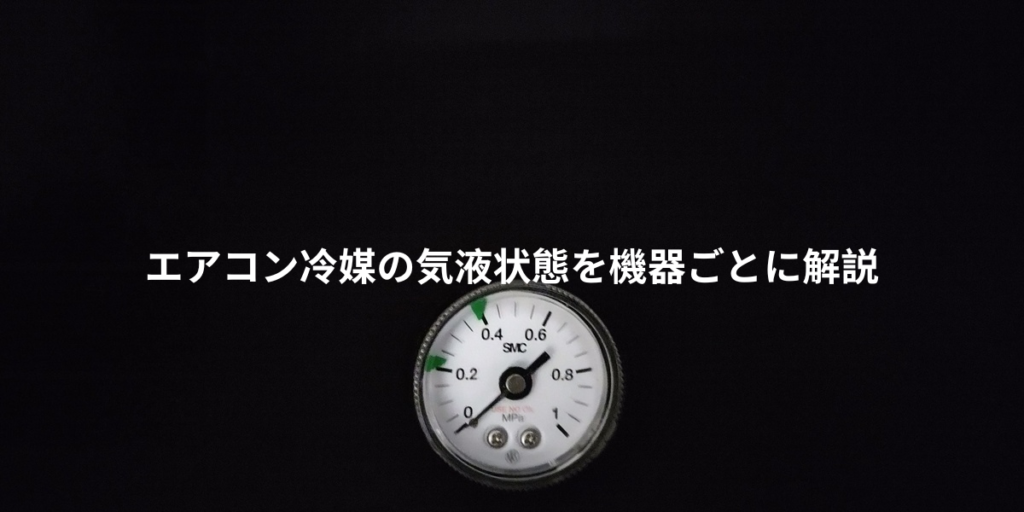
【エアコン基礎】冷媒の気液状態を機器ごとに解説します
エアコンでは冷媒が高温高圧の気体から低温定圧の液体まで幅広く状態が変化するため、室内機・室外機において冷媒がどのような状態になっているか知らない方も多いのではないでしょうか? このページでは冷房運転のエアコンにおいて冷媒がどのようなサイク... -
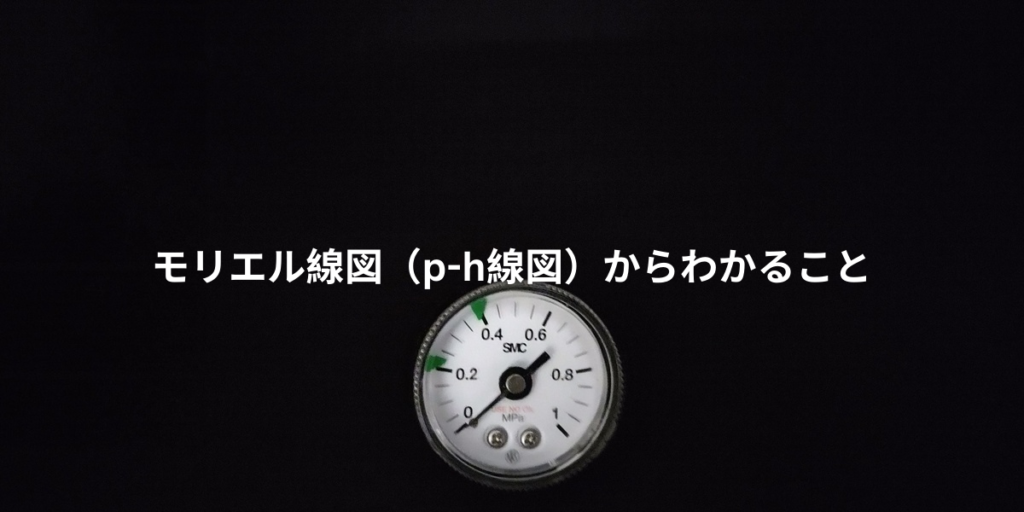
【3選】モリエル線図(p-h線図)からわかること
このページでは、モリエル線図(p-h線図)からわかる3つのこと(消費電力以上に冷房できる理由、運転の異常検知、冷房機器の性能計算)を紹介します。 冷房機器の各工程における冷媒の圧力・温度を把握できるモリエル線図は設計段階から運転保守に至るまで... -
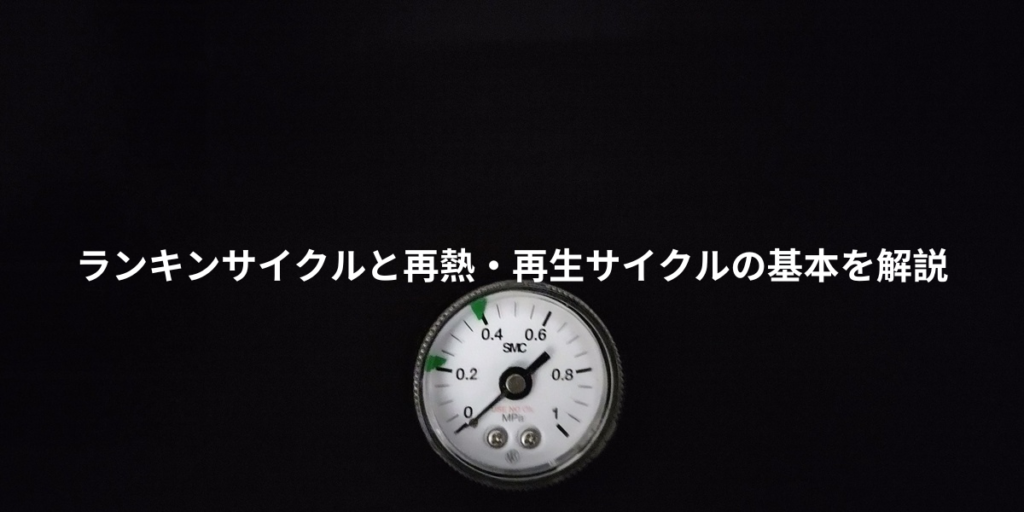
【T-S図でわかる】ランキンサイクルと再熱・再生サイクルの基本を解説
このページでは、タービンを水蒸気で回す際の熱サイクルであるランキンサイクルを紹介します。 ランキンサイクルは火力発電所や原子力発電所で電力を作るための基本となる熱サイクルなので、我々の日常生活に欠かすことはできません。 また、再熱サイクル... -
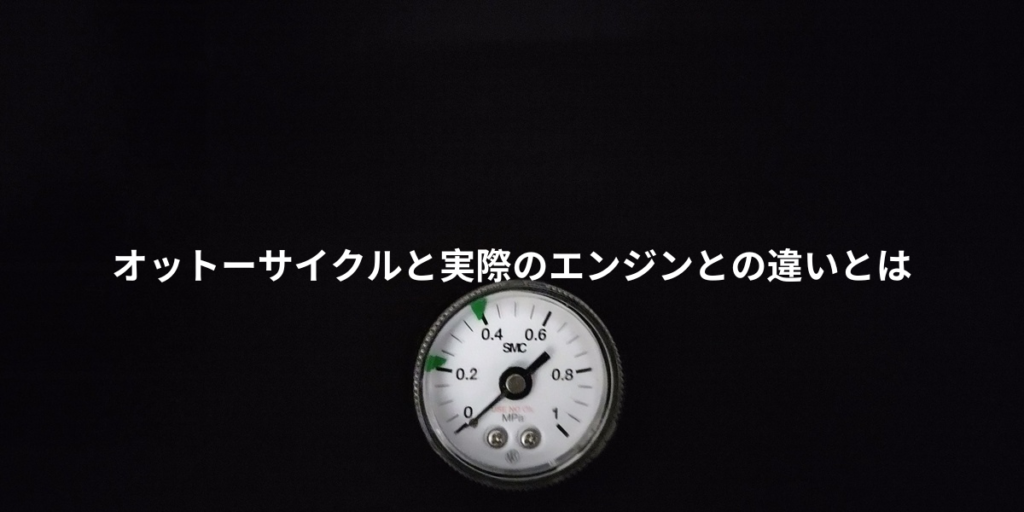
【理想と現実】オットーサイクルと実際のエンジンとの違いを紹介
身の回りで熱力学が重要な役割を果たしているひとつに車のガソリンエンジンがあります。 このガソリンエンジンのサイクルを模したものがオットーサイクルで、断熱工程と定積工程のみから構成されるため、非常にシンプルなモデルです。 このページでは理想... -
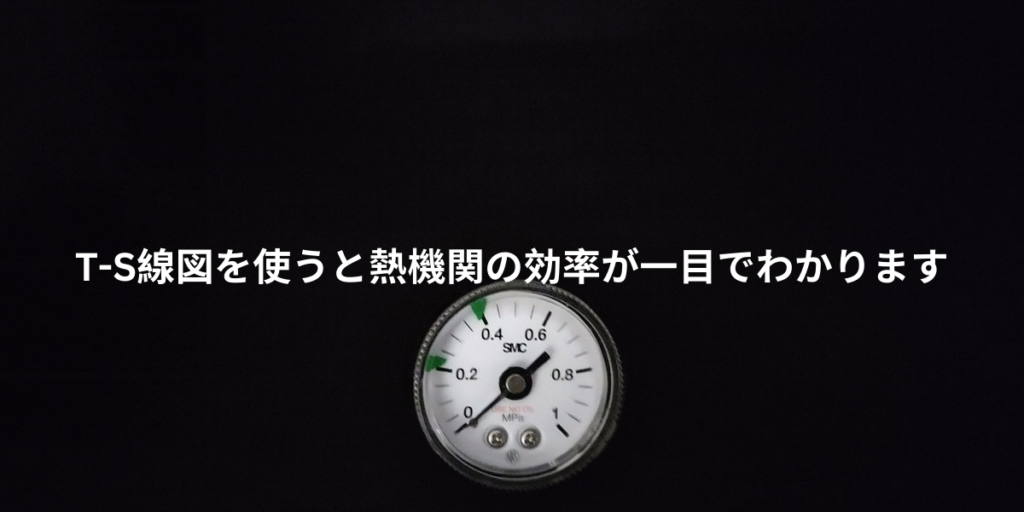
【形でわかる】T-S線図で熱機関の効率の良しあしを調べよう
T-S線図はP-V線図よりもなじみが薄いかたも多いかと思いますが、実はT-S線図を使うと熱サイクルの効率がなぜ低下するかを視覚的に知ることができます。 このページではカルノーサイクルの特徴を簡単におさらいした後、カルノーサイクルがT-S線図ではきれい...